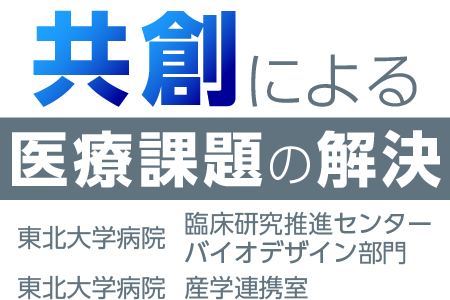ニュース
イベント2024.11.13
【産学連携室:中川】青木智乃紳先生講演会を開催しました(2024年11月11日)
2024年11月11日 厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 青木 室長補佐による講演会を開催しました。
概要は以下のとおりです。
※本講演は本人のボストン留学中の研究内容の一部を紹介するもので、所属組織の見解とは一切関係がございません
医系技官がハーバードとMITで学んだこと: 一人一人の命、皆の命を救うイノベーション実現の処方箋
~CRISPR治療薬とCOVID-19ワクチン開発の事例から~
医療とは、究極的には人間の命を救うことを目的とした活動ですが、そのイノベーションの代表例として、患者の生物学的特徴に最大限配慮した「個別化医療」や、COVID-19のような公衆衛生危機の状況においては「ワクチン」が挙げられます。本講演では「命を救うためのイノベーションを実現する方法」について、医系技官としての職務経験やハーバード(公衆衛生学修士)とMIT SDM(工学・経営学修士)での学びを踏まえ、CRISPR治療薬とCOVID-19ワクチン開発の事例を交えつつ、医学・科学技術・社会科学的側面から議論しました。
講演前半は、本人が医療経済研究機構「アメリカ医療保障制度に関する調査研究報告書2023年度版」に寄稿した内容を紹介し、技術評価や持続可能な医療制度とイノベーション促進の適切なバランスといった「イノベーション実現の前提となる考え方」について考察しました。2023年12月にFDAが承認した、鎌状赤血球症患者を対象としたCRISPR技術を応用した治療薬Casgevyの事例を踏まえ、本治療が生まれた背景、医療技術評価の枠組み、イノベーションの社会的評価、日米の薬価際等の背景となる日米の医療制度の違い、これら課題に対して日米での取り組み、個別化医療の進展がもたらす希望、それに伴う高額なコストが医療制度に与える影響について考察したうえで、持続可能な医療制度とイノベーション促進の適切なバランスについて議論を深めました。
講演後半は、本人のMIT SDMでの修士論文「製薬会社がプラットフォーム戦略を活用する方法:COVID-19 mRNAワクチン開発について研究(Aoki, Tomonoshin. How Pharmaceutical Companies Utilize Platform Strategy: A Study of the COVID-19 mRNA Vaccine Development. Massachusetts Institute of Technology, 2024.)」の内容を紹介し、イノベーションの実現に成功した開発企業の特徴やその社会科学的メカニズムといった「イノベーション実現に必要な要素」について考察しました。COVID-19のワクチン開発におけるModerna社やBioNTech社を事例に、それらの企業がどのように数十年にわたる基礎技術の開発を踏まえ創業し、どのように技術を蓄積し、いかにそれらの技術を活用してCOVID-19のワクチンが開発されたのか、他社と比べてなぜ早期のワクチン開発が可能だったのかを考察したうえで、その背景にある社会科学的メカニズムについて議論しました。
当日は、30名を超す参加者を得、熱心な質疑も行われました。
(当日の会場の様子、写真左、青木室長補佐)

青木室長補佐より、
「この講演が、医療者・医学研究者には医療・医学・科学技術を政策等社会科学的側面から捉える際のフレームワークとなり、管理的業務に携わる方や、社会科学の研究者には経営・社会科学的側面から医療・科学技術的事項を取り扱う際の枠組みとなり、それぞれのバックグラウンドを超えて、聴講いただいいた方の気づきや行動につながる契機となることを願っています。」
との総括をいただきました。