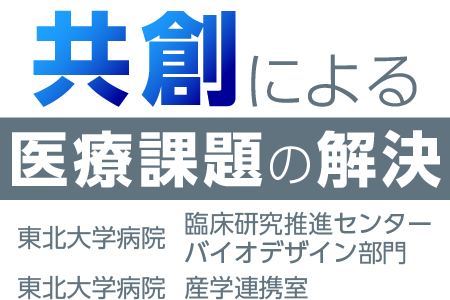事例紹介
CASE02製品開発
ASUプログラムで広がる視野とビジネスモデル

日本電気株式会社
2024.11.7
ASUの参加に至るまでの経過
NECは長期にわたり、東北大学様と協働してまいりました。参加動機は、弊社トップマネージメントが東北大学の青木副学長(当時、現在理事)からご紹介を頂いたのがきっかけです。同席していた研究企画部メンバーが応募を呼びかけており、当時は、研究所、事業部の専門家が多くの時間を割いて、健康延伸を含む新事業の技術戦略を喧々諤々と議論していました。自分達なりに、弊社の技術・リソースを生かして高齢者の皆さまに一日でも長く、健康でいてもらう為のお役に立つとともに、増大する医療費・介護費の抑制と産業振興を介した将来の社会保障費の充実という社会課題に取り組みたいという想いはあったものの、どの様な形で課題設定をすべきか悩んでいました。また、医療現場で実際に患者さんや医療従事者の困りごとを実際に自分の目で見ないと、本質的なニーズがどこか抜け落ちてしまうのではないかという不安、また、開発したものを改良し、エビデンスを蓄積できるのは医療現場との密な連携なくしてできないものの、どのようにしたらよいか、あてもなかったのです。ASUは現場観察の機会はもちろん、このプログラムに参加することで、東北大学病院、東北大学を基盤としたネットワークで重要なパートナーと触れられる機会があると考え、すぐに応募しました。
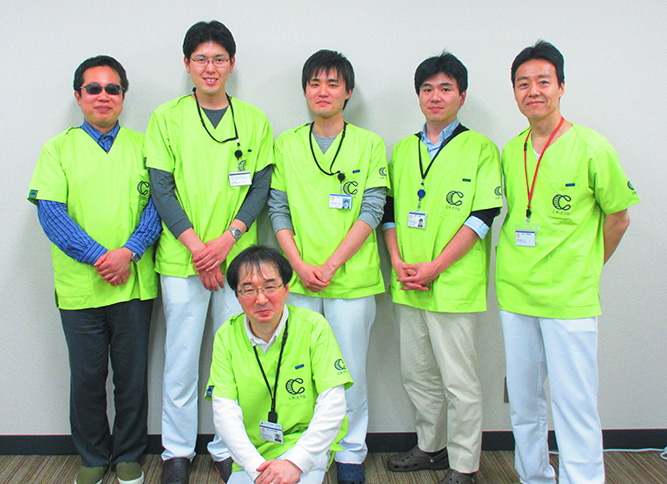
ASUに参加して解決した課題、得られたもの
プログラム開始時点で、特定のプロジェクトを念頭におき、ニーズの把握、実態調査を行う選択肢はありましたが、あえて自分の専門分野を忘れて医療現場を観察し、関係する人、モノ、業務フローをみることで多くの学びがありました。その過程で、医療スタッフ、患者さんとのコミュニーケーションの取り方からも多くを学びましたし、私たち自身が企業として、エンジニアとして、改めて、何ができるのかという使命感、モチベーションが大いに高まるきっかけになりました。考え抜いてきたとはいえ、自分たちがオフィスで考えてきた狭い技術領域に関連するニーズ探索にとどまらず、自分たちが開発した技術やサービスがどういったインパクトを誰にもたらすか、また、その結果がどういう将来のビジネスモデル、事業化につながるのかまで、ヒアリングと医療スタッフとの徹底した議論を行うことで、介護保険や地域包括ケアを含む幅広い視野で医療ニーズやビジネスモデルの整理ができたと思います。その結果、新たな研究テーマの早期立ち上げが可能になり、弊社が得意とする技術を利用し、課題領域の設定、適切なスコーピングを行った上での研究開発につながっています。ASUで得られた研究課題は、弊社と東北大医工学研究科との共同研究に発展し、その成果の一部は弊社内の事業化に向けた製品PoCや他社との協業につながる共同研究への呼び水となる等、大きな相乗効果を生み始めています。
昨今、技術の陳腐化、カスタマーの興味の関心のうつりかわりがこれまでになく短期化しており、今後もさらに加速する中にあって、現場に入り、デザイン思考などの方法論も使いながら事業化に資する課題設定からコンセプトだしまでを高速に行う新しい日本のものづくりにの提案に向けてASUからこれまで以上のしかけを期待します!
担当者の声
社内のロボット戦略で、高齢者の健康延伸の鍵は「歩行」と定め、社会課題を解決するロボットやAIサービスのニーズ・研究テーマ探索を目的にASUに参加しました。
当初は医療向けロボットのニーズ把握、実態調査が目的でしたが、まず医療の現実、スタッフの導線を知ることで、医療スタッフや患者さんとのコミュニーケーションの取り方を学んだほか、モチベーションが大いに高められました。狭い技術領域のニーズ探索にとどまらず、ヒアリングと議論を行うことで、将来どんなビジネスモデルや事業化につながるか、介護保険や地域包括ケアを含む幅広い視野で整理ができたと思います。その結果、新たな研究テーマの早期立ち上げが可能になり、弊社が得意とするIoTセンシング基盤技術、システム技術を利用した在宅医療ビジネスに資する歩行計測・ロボットの研究開発につながっています。さらに本研究は、弊社と東北大学医工学研究科との共同研究に発展し、成果の一部は弊社内の事業化に向けた製品PoCや他社との共同研究への呼び水となる等、相乗効果を生み始めています。
※2019年6月時点の内容です。